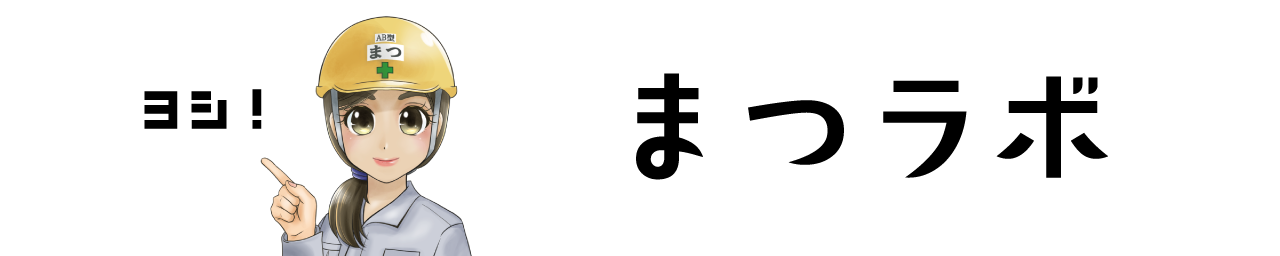知性の危機としての時代
「理性の時代」と呼ばれた近代は、知性を社会の指導原理として位置づけた。
しかし、ハンナ・アーレントが『人間の条件』において述べたように、
「思考することを放棄した人間は、どんなに理性的であっても、世界と自分自身を見失う」(ハンナ・アーレント『人間の条件』)
とき、理性はもはや自由の根拠ではなく、思考の停止を生み出す。
知性は世界を理解する手段であると同時に、しばしば世界からの疎外を生み出す装置ともなり得る。
また、オルテガ・イ・ガセットは『大衆の反逆』で次のように述べた。
「専門家は、もはや自分が無知であることを知らない無知者である。彼の知識は限られており、それ以外の世界には盲目だ」(オルテガ・イ・ガセット『大衆の反逆』)
オルテガのこの指摘は、近代社会における「インテリ層」が、専門知に閉じこもることで「生きた知性」を失う危険を示している。
知性が社会的現実に根を持たなくなったとき、それは権威的形式へと退化し、思考の自由を抑圧する。
このような文脈において、「反知性主義」という言葉を単なる反知的風潮として退けるのは早計である。
むしろ、知性そのものが自己を絶対化する過程において、知性が自らを反省するための契機として「反知性主義」を捉え直す必要がある。
すなわち、ここで問われているのは「知性への反抗」ではなく、「知性主義への抵抗」なのである。
「反知性主義」という語の再考
「反知性主義(anti-intellectualism)」という語は、一般には「知的努力を軽視し、感情や信仰を優先する態度」として理解される。
しかし、この理解はあまりに表層的である。
本来問題にすべきは、語の構造そのものである。
「反知性主義」は**“反・知性主義”であって、“反知性・主義”**ではない。
すなわちそれは、「知性を否定する思想」ではなく、「知性を特権化する主義(知性主義)」への批判的姿勢でありうる。
この区別を見失うと、知的営為そのものが自らを絶対化し、社会的権威として固定化してしまう危険を孕む。
知性主義の権威化とインテリ層の閉鎖性
近代社会において、知識人や専門家層は「理性による社会の統御」を理念として、一定の地位を築いてきた。
しかし、この過程で「知性」はしばしば制度化された権威として機能し、批判よりも正当化に奉仕する存在へと変質していった。
アーレントは、官僚的思考の危険を指摘しながらこうも述べている。
「凡庸さは思考の欠如から生じる。思考しないことが、最大の悪を可能にする」(ハンナ・アーレント『エルサレムのアイヒマン』)
知性が権威へと堕するとき、それは思考ではなく命令の体系となる。
「知性」が権威となるとき、それは自らの正統性を維持するために「非知的なもの」を周縁化する。
こうして生まれるのが、知的ヒエラルキーであり、そこでは「理解しない者」「異なる者」「感じる者」は、しばしば「反知性的」として退けられる。
この構造のもとで、「知性主義」は自己防衛的となり、社会的正義の名のもとに批判を免れる。
だが、真に知的であるということは、自己の前提をも疑うことに他ならない。
インテリ層による「反知性主義」の可能性
ゆえに、真に必要なのは、インテリ層が自ら反知性主義的になることである。
ここで言う「反知性主義」とは、知を軽んじる態度ではなく、知が制度化される過程を批判的に省みる姿勢を指す。
知的営為が社会的権威へと堕するのは、それが自己批判を放棄したときである。
知性が自らの限界を引き受け、思考の枠組みを絶えず再構成していくことこそ、知の生きた運動である。
「反知性主義」とは、知の外部を拒絶するのではなく、むしろ外部との接触を通じて知を更新しようとする意志である。
オルテガは「大衆の時代」における知性の危機をこう表現した。
「文化とは、常に自己批判を内に含むものでなければならない。自己を疑わぬ文化は、もはや文化ではない」(オルテガ・イ・ガセット『大衆の反逆』)
したがって、知性の側からの反知性主義は、知的営為の自己防衛ではなく、その自己超克の形である。
反知性主義を拒む知性の堕落
現代社会では、「反知性主義」という語がしばしば政治的・文化的レッテルとして使われる。
インテリ層はそれを「非合理」「ポピュリズム」として排除し、自己の立場の正当性を確保する。
しかし、その態度こそが、知性の自己閉鎖に他ならない。
批判されない知性はもはや知性ではない。
知的主体が「反知性主義」を忌避することは、自らの思考がすでに硬直していることの証左である。
知性は、常にその外部を必要とする。
外部なき知は循環し、やがて権威へと堕する。
したがって、「反知性主義を拒む知性」は、形式的な理性を保持しながらも、内容的には反知性的であるという逆説に陥る。
それは知性の名を借りた無反省な信仰であり、「知的なるもの」の形をした無知に他ならない。
知性の再生は自己懐疑から始まる
真に知的であるとは、自己を疑う能力を持つことである。
知性が「自らを批判する力」を失ったとき、それは単なる支配の言説へと変わる。
したがって、知の倫理は「反知性主義」を敵視することではなく、それを自らの内部に引き受け、知の自己批判的更新へと転化させることにある。
反知性主義とは、知性がその限界を自覚し、他者や感情、非体系的な思考を通じて再生する契機である。
知性が「知性主義」を脱し得たとき、初めて知は自由になる。
知を信じるとは、知を疑う勇気を持つことである。
そしてその懐疑こそが、知性を再び生きたものへと解放する。
〈結語〉
反知性主義を拒む知性こそ、もっとも反知性的である。
知性とは、自己の偶像を破壊しつづける営為であり、
反知性主義とは、その破壊の運動を内に孕む知のもう一つの名である。